昨日、今話題の映画「侍タイムスリーパー」を見てきました。文字通り、侍がタイムスリップするSFコメディといった感じなのですが、まさに「虚と実」を織り交ぜ、上手く緩急をつけて見る人を引き付ける良い作品でした。ストーリーが素晴らしく、素直にクスッと笑ってしまったり、反対にウルッとさせられたり、ハラハラドキドキさせられたりと、感情を揺さぶってきます。
嘘っぽく(安っぽく?)ならないようにディテールにはこだわっているように感じました。しかし、終盤での真剣を用いての斬り合いでちょっと疑問に思うことがあったので、ChatGPTに聞いてみました。
質問:
時代劇の殺陣のシーンでは、よく何度も刀どうしを当てるシーンを見ますが、あまり現実的ではないと感じます。竹光や竹刀、木刀などであればぶつけ合っても問題ないですが、金属製の真剣どうしとなるとそうはいかないと思います。軽く当てただけでも刃こぼれを起こすと思うし、重い真剣どうしを大の大人が思い切り振ってぶつけ合えば刀自体折れてもおかしくないと思います。実際の真剣勝負とは、もっとシンプルで地味であり、一度斬り合いに使った刀はかなりの確率で使い物にならなくなるのではないでしょうか。
回答:
おっしゃる通りです。時代劇でよく見る「カチカチと刀を当て合う殺陣」は、エンターテインメント性を重視した演出で、実際の真剣勝負とは異なる部分が多くあります。現実の戦いでは、刀を直接ぶつけ合うのはリスクが高く、刃こぼれや破損の可能性が高まります。そのため、できる限り接触を避け、相手の隙を突いて一撃で勝負を決めることが理想的でした。
真剣での戦闘では、刀が長時間の耐久力を持つことは少なく、戦いが終わった後は修理や刃を研ぎ直す必要が生じることが一般的でした。また、日本刀は切れ味が高い反面、他の金属と衝突すると非常に脆くなるため、現実的な剣術では相手の刀を直接受けるより、角度や技でかわしたり、力をそらしたりする工夫がされていました。
時代劇や特撮などでは、こうしたリアルな戦闘よりも、観客にわかりやすい迫力あるシーンが求められるため、刀をぶつけ合う演出がよく取り入れられていますね。
追質問:
日本刀は、合戦では攻撃する武器としては実用的ではなく、もともと打ち取った相手の首を落とすために使ったと聞きましたが、本当でしょうか。だとすると、いつごろから武士がたえず身に着け、魂のように大事にするようになったのでしょうか。
回答:
確かに、日本刀は合戦の主力武器としてよりも、戦場で打ち取った相手の首を落とすためや護身用の武器として携帯されることが多かったとされています。戦国時代の大規模な戦闘では、間合いのある槍や長柄武器、弓や火縄銃が主力で、日本刀は接近戦での補助武器のような役割が一般的でした。戦場では、刀を振るうこと自体が体力の消耗を伴い、実用的な殺傷力を考えた場合には、遠距離や集団戦に適した武器が重宝されました。
一方で、刀が武士の「魂」として重視されるようになったのは、戦国時代を経て戦が少なくなり、江戸時代に入ってからとされています。この時期には、刀は実戦での使用よりも、武士のアイデンティティや社会的地位を象徴するものとしての価値が高まりました。江戸時代には「帯刀」が武士階級の特権となり、「一刀一拝」といって刀を神聖なものとして礼拝する風習も生まれました。
このようにして、刀は戦場での実用的な武器という側面から、武士の精神性や美意識、礼儀作法と結びついた象徴へと変化していったのです。
所感:
もともと殺傷力としては実用性の低い刀が、戦が少なくなってきた世で帯刀という武士の特権のために使われるシンボルとして神聖なものになっていったようですね。命のやり取りを伴う真剣勝負から、スポーツとしての剣道やエンターテインメントとしての殺陣が生まれたことも興味深いです。

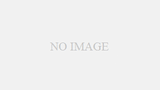
コメント